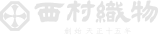西村織物について
創始天正十五年
輝く絹とともに
古来より「極細の宝石」として
世界中の人々が憧れてきた、絹。
天正十五年(1587年)、
西村家は絹糸の商人として創始以来、
絹と向き合ってきました。
江戸時代には博多織屋を創業。
博多織最古の織元として、
今も織物の可能性を追究しています。
年月が流れても、輝く絹とともに、
帯や、着物を愛する人々を輝かせるために。
職人たちの技術を紡ぎ合わせながら、
これからもずっと絹の世界を広げていきます。
Shine, people.


最古にして先端の
織屋として一歩ずつ
貿易という荒波に挑戦した、戦国時代。
織屋として新しいビジネスに挑戦した、江戸時代。
博多織最古の織元という歴史を受け継ぎながらも
伝統という枠にとらわれない、先端の織屋でありたい。
そんな希望を胸に、絹の可能性を信じ、
世界に通じる織屋になれるよう精進してまいります。

西村織物の歴史
貿易商から博多織の織屋へ
430年以上の時を絹と歩いて
西村織物と絹が出会ったのは戦国時代。
幾つもの時代を超えて、今なお絹を輝かせています。
創始
一五八七年~
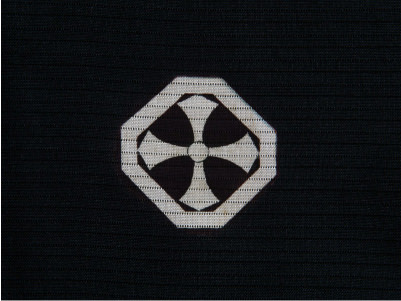
西村 増右衛門
絹糸の貿易商人として
博多のまちへ
西村家の祖先である長崎の豪族(松浦党)の西村増右衛門は、天正五年、大友宗麟の乱を避けて博多へと移住。その後、天正十五年(1587年)に豊臣秀吉の博多町割に参画、神屋宗湛を助けた功により、朱印状を授与され絹糸の貿易商人としての歴史が始まりました。西村家の家紋であり、会社のロゴマークである「隅切り角に四つ剣菱」の紋は、豊臣秀吉より授与されたものです。(筑前国風土記第四巻より)
織屋初代
一八六一年〜

西村 儀平
博多織の世界へ
江戸末期、江戸幕府が海外への金銀流出を防ぐ政策をとったことから、絹糸の輸入が制限されるようになりました。そこで当時の西村家の当主、西村儀平は思い切って事業の方向性を転換。博多織屋株の雄、白水長左衛門のもとで絹織物の技術を修得し、1861年(文久元年)に西村織物を創業します。江戸末期はすでに絹織物である博多織の着用が、庶民に許されていた時代。男性用の帯が多く織られていました。
二代目
一八八〇年〜

西村 清吉
帯の品質を
守るために奮闘
政治問題や物価の高騰など、さまざまな社会不安が世の中を覆った明治時代初期。粗悪品の帯が出回り博多織は著しく社会の信用を失います。この問題を受けて、博多織の品質を保つために博多織会社が結成されたのが1880年(明治13年)のことです。2代目・清吉はその立ち上げに指導的な立場で参画し、博多織の品質の向上に努めました。
三代目
一九一〇年〜

西村 清次郎
大相撲との
深い絆をつくる
大正時代になると、力士の化粧廻しや締め込みを織るようになり、西村織物は相撲界との強い繋がりを築いていきます。
しっかり硬く結べて、肌触りの良い化粧回しの評判は上々。
3代目・清次郎は“木戸御免”となり、相撲部屋に自由に出入りしながら商いをするようになりました。
四代目
一九四八年〜

西村 政太郎
西村織物の中興の祖
太平洋戦争中の1942年(昭和17年)、贅沢を禁じる奢侈禁止令により、西村織物は操業停止に追い込まれます。4代目・政太郎は太平洋戦争の徴兵を受け、出征。さらに1945年(昭和20年)の6月19日、福岡大空襲で博多区奈良屋町の自宅、工場、会社を全て焼失してしまいました。1948年(昭和23年)、復員後の政太郎が、博多織製造を福岡市本庄町天神(現在の今泉)にて再開。手織の織機で、伊達締めを織ることから始めました。裸一貫、焼け野原からの西村織物再興です。
優秀なビジネスマンだった政太郎は、1957年(昭和32年)になると手織から機械織への移行を成し遂げます。1961年(昭和36年)には社名を西村織物株式会社に変更。西村織物を懸命に育て、規模を拡大させた中興の祖です。現在、本社がある筑紫野市の工場には最盛期で100名を超える職人さんが働いており、八女にも第2工場がありました。そして1974年(昭和49年)、博多織の需要はピークを迎えます。織元も200軒を超え、福岡を代表する産業となりました。
翌年には、博多駅まで山陽新幹線が開通。博多の土産物としても博多織の帯が飛ぶように売れました。
相撲、歌舞伎、落語など
日本の文化を支える帯
丈夫で締め心地のいい博多織の帯は長らく日本文化を支えてきた存在です。現在、西村織物は、伝統芸能の担い手の方々が通う浅草の帯専門店「帯源」の看板商品「鬼献上」を別注にて織らせていただいています。そのおつきあいは四代目の政太郎の時代から。歌舞伎俳優、噺家、邦楽演奏家などに幅広くご愛用いただき、“オニケン”の相性で親しまれています。
新技術を独り占めしない
博多の男気と優しさ
4代目・政太郎は頭の切れる人物で、博多織の人気上昇にともない角帯など幅が細い帯を一度に複数織れる織機を開発しました。政太郎はこの織機の存在を隠そうとせず、むしろ同業者に勧めてまわり、製造方法を伝授。博多めんたいこの製造方法を広く教えたふくや創業者と同様、博多織産業全体の発展に貢献したいと考えていました。そんな政太郎がつくった社訓は「誠実是最上」。いつもどんなことに対しても誠実であれという教えです。
五代目
一九八二〜

西村 悦夫
妥協なくこだわり抜く
職人気質
1982年(昭和57年)、5代目・悦夫が社長に就任します。悦夫はものづくりが好きで、織物の品質に徹底的にこだわる人間。織物に対するゆるぎない姿勢は、西村織物の職人はもちろん、取引先にまで知れ渡っていました。そのような超・職人気質の悦夫ゆえ、呉服業界が斜陽産業となっていくなかでも、高品質なものづくりを確立します。博多織において伝統的な平地に加え、紋地の織物を開発。さらに一職人として、ほかの職人たちと協力しながら、これまで手掛けていなかった織物技術を積極的に取り入れました。こうして博多織のニーズ減退のなか、少ロット多品種という厳しい条件ながらも、西村織物は進化を続けることができました。
六代目
二〇一六〜

西村 聡一郎
最古であり
先端であること
2016年(平成28年)、6代目・聡一郎が社長に就任。伝統に培われた技術を最大限に生かし、織物の可能性を広げています。社内一貫生産体制を作り、染色やデザインなどを内製化。糸づくり以外のすべての工程を西村織物内で可能にしました。また博多織を世に知ってもらうべく他業種とのコラボレーションにも積極的に参画。最古にして先端であることを意識しながら次世代に事業をつないでいます。
制作理念は「絹よ輝け、人よ輝け」。お客様はもちろん、職人、技術、歴史を輝かせることのできる織屋であることに努めています。




伝統だけでなく
織物の可能性を追究。
日本の伝統である絹織物のバトンを次代に継承するとともに、
絹織物の可能性を広げるため、多様なプロジェクトに挑戦しています。
広幅織機の技術を活かしたインテリアへの新しいアプローチ、
他業種の企業との幅広いコラボレーション、
絹のアップサイクルを意識した新ブランド「ObitO」リリースもそのひとつです。